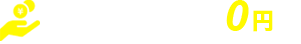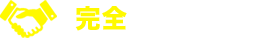みなさんは、「過失割合」という言葉をご存知でしょうか?
中には、保険会社から過失割合を提示されて、何が何だかわからなくてこちらにやってきたという方もいらっしゃるかもしれません。
普段聞きなれない言葉であるためこれも仕方がないことです。
過失割合とは、当事者のどちらかに交通違反や不注意があった場合、果たしてどちらに責任が大きいのか、その割合を表したものです。
交通事故ではこの過失割合によって、最終的な損害賠償額が決まることになっているため、無視して通ることのできない問題の1つとなっています。
今回は、この過失割合の重要性と弁護士のサポート内容についてご説明します。
過失割合の決め方について
最初に過失割合に決め方について知っておきましょう。
実は過失割合には一定の相場が決まっていて、これは過去の裁判例などをもとに決められています。
裁判においては大まかに、当事者の状況や交通状況、その他の特殊な事情について考慮され、最終的な過失割合が算定されるのですが、実務においては「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という書籍をベースに算定されるケースがほとんどです。
もちろん裁判においても、この書籍が抜粋されて証拠書類として提出されることもあります。
よって、よほど特殊な状況でない限りは、過失割合はそれほど揉めずに決められることになります。
しかし、事故状況のすべてが書籍通りに当てはまるわけではないため、交渉によって結果が左右することも当然あります。
こういった点は、まさに弁護士の腕の見せ所と言えるでしょう。
過失割合が重要な理由とは?
では、なぜ過失割合が重要と言われているのでしょうか?たとえば、治療費や慰謝料、休業損害に逸失利益など、すべての保険金総額が1000万円だったとします。
過失割合以外の部分については、それぞれ個々に計算され、それが積みあがって保険金総額が算定されています。
しかし、過失割合は、この保険金総額に対してかかってきます。
これがどういうことかというと、過失割合が2:8となると、受け取れるはずだった保険金総額から2割が相殺され、800万円しか受け取れなくなってしまうということ。
これを過失相殺といいます。
個別に積み上げてきた金額から、割合でばっさり引かれてしまうことからも、2:8が1:9になっただけで10%もの金額を手元に残せることになるのです。
800万円が900万円になるという、実際の数字でみてみると、過失割合が重要たる所以が伝わるのではないでしょうか。
過失割合で揉めたら弁護士に相談を
上記からもわかるように、過失割合の違いで最終的に受け取れる金額に大きな差額が出てきます。
もし、過失割合で保険会社と揉めた場合は、失敗しないためにも弁護士に相談しましょう。
弁護士であれば、警察が作成した実況見分調書をもとにした事故状況の検討、実際に事故現場に足を運ぶ現地調査など、過失割合を有利にするためのサポートが可能となっています。
しかし、現実には、保険会社の言われるままの方も多く、とても正当とはいえない過失割合にて示談へと至るケースも多数見受けられます。
保険会社は決して被害者の味方ではありません。
自社にとって有利な過失割合を認めさせることで、保険金額の支払を軽減しているのです。
とはいえ、個人が保険会社と交渉しようと思っても、過失割合に関連する知識(裁判例の知識)などが不足している一般の方に反論などできるわけがありません。
不当な損を被らないためにも、保険会社側と過失割合で揉めたら、いったん交渉はストップし、弁護士に相談するのが賢明です。
過失割合でお困りなら当事務所にご相談を
過失割合の交渉では、物損の過失割合が傷害の過失割合に引き継がれることが多いのですが、個人と保険会社とで交渉していると、不利な物損の過失割合がそのまま引き継がれてしまい、それを何の疑問に思わない方もいらっしゃいます。
しかし、物損と傷害の過失割合はイコールではありません。
当事務所では、こうした保険会社とのズレを修正するため、ご相談者様から事故の様子を詳細に聞くことで、適正な過失割合になるよう調整いたします。
また、事故現場があまり遠い場合、現地まで足を運ぶのが難しいこともありますが、事情次第では実際の現場を見にいくこともありますし、ご相談者様から現場の写真を提供してもらうこともあります。
こうすることで、より詳細な現場状況を整理・確認し、保険会社側が提示してきた過失割合が本当に適正かどうかを判断しています。
また、過失割合はたった1割の違いで何十万、何百万と金額が変わってきます。
保険会社の提示した過失割合が妥当だったとしても、わずかでも可能性がある限り、1割の違いにまでこだわって内容を覆せるよう最大限のサポートをしていきます。
もし、過失割合の交渉で揉めている、保険会社側の提示に納得できないという方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
まずはお電話から、お気軽におかけいただければ幸いです。