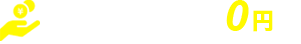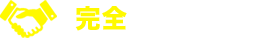交通事故によって入院や通院といった治療が必要になってしまった場合、当然、仕事は休まなければなりません。
本来得られることが出来た収入を、得ることができなくなってしまうのです。
これはまさに、交通事故による損害の一部と言い換えることができます。
一般に休業損害とは、後遺障害がある場合の症状固定や、完治までにかかった期間中に生じた損害について請求することになっています。
では、この休業損害はどのように計算していくのでしょうか?今回は、主婦・サラリーマン・自営業者の方について、休業損害の計算方法について詳しくみていきましょう。
主婦(主夫)の方の休業損害
休業損害は、給料をもらっている方の場合、計算はそれほど難しくはありません。
しかし、主婦の方となると、普段の家事に給料が発生しているわけではないため、そのままだと休業損害の算出ができません。
そこで、自賠責基準においては、主婦の方の1日あたりの基礎収入を5700円と定め、ここに休業にかかった日数をかけることで休業損害を算出しています。
なお、自賠責基準はあくまでも最低限度の補償でしかありません。
裁判所基準においては、賃金センサスを基準とし、女性の全年齢平均賃金の年収を365日で割った金額を1日あたりの基礎収入としています。
賃金センサスは、毎年数字が若干異なるため、その年ごとに計算しましょう。
ただし、すべての主婦業を制限されていなかった場合、どの程度の割合で制限されていたのか、パーセンテージをかけなければなりません。
たとえば、休業損害の期間が1ヶ月だったとします。
そして、そのうちの1週間は入院し、残りは通院によって30パーセントの主婦業が制限されたとすると、1週間分の休業損害と、3週間分の休業損害から30%を引いた金額が休業損害です。
サラリーマンの方の休業損害
サラリーマンの方は主婦の方とは違い、給料にてすでに1日あたりの金額が数値化されているため、休業損害の計算はそれほど難しくはありません。
一般的な方法としては、事故前3ヵ月間の総支給額を90日で割り、ここで出た数字を1日あたりの基礎収入とします。
基礎収入が算出されたあとは主婦の方の場合と一緒で、休業にかかった日数をかけることで休業損害を算出します。
なお、事故後の入通院の期間中に有給休暇を使用していたとしても、休業損害に影響が出ることはありません。
なぜなら、交通事故に遭っていなければ、事故後の入通院に有給休暇を使用する必要などそもそもなかったのです。
また、休業期間がボーナスに影響した場合や、減給といった処分が下った場合、予定されていた昇給が白紙になったなど、そういった特別な事情があった場合も、一般的には休業損害にて補填することが認められています。
自営業の方の休業損害
自営業者の方の場合、主婦の方のように収入が数値化されていないわけではありませんが、サラリーマンの方のように給料があるわけではありません。
とはいえ、1日あたりの基礎収入を算出し、ここに休業日数をかけるという計算方法は一緒です。
そこで問題になるのが、自営業者の方の1日あたりの基礎収入をどのように算出するかです。
サラリーマンの方のように3ヵ月間の収入を90日で割るという方法は、収入に波のある自営業者の方からすれば不利になってしまう可能性が十分あります(逆に有利になる可能性もありますが)。
よって、この有利不利をなくすために、自営業者の方の場合は、年収を365日で割った数字を1日あたりの基礎収入とするケースが多くなっています。
年収の確認方法については、確定申告書を用いるのが一般的ですが、確定申告を個人でされている方の場合、間違った数字を出してしまっている恐れもあるため、万全を期すのであれば、税分野の専門家である税理士に確認してもらうのも良い方法の1つです。
休業損害のお悩みは当事務所にご相談を
このように、休業損害の計算方法はどういう立場の方かによっても変わってきます。
特に、主婦の方の場合、休業損害の請求をしないままでいると、あえて保険会社側から声かけてしてくれることもなく、休業損害を得られないまま示談してしまったなんて方もいらっしゃいます。
また、自営業者の方でも、中には確定申告をしていなかったという方もいるので、そういった方の場合、1日あたりの基礎収入の算出が単純ではなくなってしまいます。
当事務所では、交通事故問題に特に力を入れているため、こうした休業損害にかかるトラブルに対し、適切なアドバイスをさせていただいています。
ちょっとした休業損害の計算方法についての疑問から、保険会社との具体的な交渉、示談までに確認しておくべきことなど、依頼するまでには至らないまでも、専門家からのアドバイスが聞きたいという方は、ぜひご利用いただければ幸いです。
当事務所は、初回相談を60分無料で実施していますので、お気軽にお声かけください。