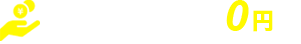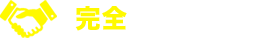交通事故が業務中に起こった場合、労災保険を利用することができます。
労災保険は必ず利用しなければならないわけではなく、通常は自賠責保険の利用で問題がない場合もありますし、特にどちらを使えという法律上の規定もありません。
過失割合次第では、労災保険を利用したほうが良いケースも存在します。
ただし、損害補償の重複を防ぐために、労災給付が先にあった場合、自賠責保険における損害補償ができなくなる点にだけは気を付けましょう。
今回は、過失割合に影響を受けない、労災保険を使うメリットについて見ていきましょう。
労災保険の使い方
冒頭でも触れたように、労災保険が利用できるのは業務中に起こった交通事故の場合です。
この条件を満たし、労災指定病院で治療を受けるのであれば、病院にその旨を伝え、「療養補償給付(療養給付)たる療養の給付請求書」を提出します。
労災指定病院以外で治療を受けるのであれば、この請求書に治療費の領収書を添付し、労働基準監督署に提出すると、支払った治療費が振り込まれます。
交通事故の場合は、さらに「第三者行為災害届」を労働基準監督署に提出すると、労災保険を加害者の代わりに立て替えたという構図が出来上がります。
労災保険の利用がメリットになる3つの状況
では、具体的にどういった状況で労災保険がメリットになってくるのでしょうか?
労災保険の利用がメリットになる3つの状況についてまとめてみました。
1.自身の過失割合が大きい場合
通常、交通事故の治療費というのは加害者側が負担することになります。
よって、労災保険を利用していようが自由診療であろうが、被害者側が負担することはありません。
しかし、交通事故における被害者側の過失割合が大きい場合、治療費の全額請求が認めらません。
特に、自賠責保険においては、7割を超える過失割合がある場合、損害補償が2~5割程度になってしまいます。
しかし、労災保険を利用していた場合、こうした過失割合による減額がないのです。
また、過失割合について相手側と揉めている場合も、もしもの場合に備えて労災保険を利用しておくのが良いでしょう。
これは健康保険を利用した場合も同様のことが言えます。
2.運行共有者責任を相手が認めない場合
自賠責保険というのは、その対象となる車の運行供用者が事故を起こした場合に適用される賠償保険です。
しかし、交通事故の相手が盗難した他人の車を運転し、その結果、交通事故になった場合、その盗難車の所有者が運行供用者責任を認めないとなると、個人でこれを認めさせるのは簡単ではありません。
そこで、あえて労災保険を使うことで、管轄を労働基準監督署(厚生労働省)へと移行させ、求償権を行使してもらう、というのは良い方法の1つです。
3.相手が無保険だった(自賠責保険しか加入してなかった)
相手が無保険だった(自賠責保険しか加入してなかった)場合、最低限度の補償しか受けることができません。
自賠責保険では、傷害事故に対しては120万円という限度額が定められており、自由診療を受けているとあっという間に限度額に到達してしまう恐れがあります。
さらに、自由診療の場合、1点あたり平均して20円前後と、労災保険(1点12円)と比較すると高額になっています。
もし仮に、治療費だけでこの120万円を使い切ってしまうと、本来ならもらえるはずの慰謝料が一切手元に残らないということになりかねません。
このように、補償範囲や診療報酬の違いなどから、相手が無保険だった場合は、労災保険給付を優先させたほうが良いと言えます。
特別支給金も申請しよう
自賠責保険の場合、休業損害補償は1日あたりの上限はあるものの、過去3ヵ月間の平均賃金の全額を受け取ることができます。
一方で、労災保険の場合、3ヵ月間の平均賃金の8割相当額となっています。
少ないじゃないかと感じた方も多いと思いますが、しかし、この8割相当額には内訳があり、保険給付部分が6割相当、休業特別支給金が2割相当となっています。
そして、休業特別支給金については、自賠責保険にて休業損害補償を受けた場合であっても、別途申請手続きをすれば支給を受けることができるのです。
つまり、自賠責保険によって、過去3ヵ月間の平均賃金を全額受け取ったうえで、2割相当の特別支給金が受け取れるということ。
これを利用しない手はないため、申請手続きをしっかり行うようにしてください。
交通事故問題は当事務所にお任せください
上記からもわかるように、労災保険の利用は思っている以上に複雑ですし、必ずしもメリットが生じるわけではありません。
状況に応じた使い分けが必要になってくるのです。
また、交通事故問題の多くは、個々の事情に応じたケースバイケースな対応が求められます。
そういった意味でも、専門家の介入は手続きをスムーズに進めるために重要な役割があります。
当事務所は、数ある法律問題の中でも、交通事故問題には特に力を入れています。
専門家目線でのアドバイスが欲しいという方は、ぜひ一度、当事務所にお越しください。