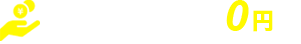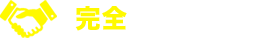まず、後遺障害というのは、一般の方が考えている、怪我や病気などの治療後に残った「後遺症」とは異なり、交通事故が原因であると医学的に証明され、かつ労働能力の低下や喪失が認められることを指します。
そして、後遺障害等級認定とは、この後遺障害の重さに応じてなされる等級認定のことで、これが被害者の方が交通事故で失った代償として得る金銭になります。
今回は、この後遺障害等級認定の申請の流れと適切な等級を得るポイントについて見ていきます。
後遺障害等級認定の手続きには2種類ある
最初に押さえておきたいのが、後遺障害等級認定には2種類の手続きがあるという点です。
1、被害者請求
被害者請求というのは、被害者自身が後遺障害の等級認定を自賠責保険会社に対して手続きを取ることです。
以下で説明する方法と比較すると、提出書類をすべて自分で用意しなければならないため、時間も手間もかかってしまうというデメリットがあります。
一方で、精査してもらえるという意味では十分すぎるほどのメリットがあると言えるでしょう。
2、事前認定
事前認定とは、相手の保険会社に申請手続きをすべて任せてしまう方法です。
等級認定に必要な書類を用意する必要がありませんし、早期解決を目指す場合に非常に有益となっています。
被害者自身も書類を集める負担が減るメリットがあります。
ただし、提出書類のすべてを確認できるわけではないため、自身にとって不利な書面が提出されている恐れもあり、必ずしも良い結果が出るとは限らないというデメリットがあります。
また、等級認定とは別に示談交渉が長引いている場合、支払い自体が遅くなることもあります。
弁護士は被害者請求を推奨するケースが多い
上記のようなメリット・デメリットがある2種類の手続きですが、基本的に弁護士に手続きを依頼している場合、被害者請求を推奨されるケースが多くなっています。
もちろん、事情によっては被害者請求でも事前認定でも結果が変わらないといった場合もあり、そういった場合は早期解決という意味でも事前認定が推奨されることもあります。
もちろんケースバイケースではあるものの、やはり被害者請求のほうが適正な後遺障害等級を得られる可能性が高いだけでなく、自賠責保険金が素早く振り込まれるというメリットもあります。
被害者請求の場合、自身の負担が大きいと感じてしまいがちですが、弁護士のサポートがあるため、言われた書類を入手するだけで手続きは進められていくためご安心ください。
なお、一度結果が出た等級認定を覆すのは簡単ではないため、初回から内容を確認しながら申請できる、被害者請求を積極的に行っていくのが適切な等級認定を得るためのポイントの1つと言えるでしょう。
被害者請求の簡単な流れについて
では、被害者請求はどのような流れで行われていくのでしょうか?といってもそれほど難しいものではありません。
被害者側が手続きに必要となる後遺障害診断書といった書類を集め、必要があれば書類を作成し、自賠責保険会社に対して保険金請求を行います。
すると、自賠責保険会社は被害者側から送付された書類の内容を確認し、損害保険料率算出機構に送付します。
損害保険料率算出機構は、送付された書類について審査し、その結果を自賠責保険会社に報告します。
最後に、自賠責保険会社は報告結果を踏まえ、後遺障害等級の認定を行うという流れです。
カギを握るのは後遺障害診断書の中身
後遺障害等級認定においてもっとも重要なのは、医師が作成する後遺障害診断書です。
この中身次第で、等級認定の結果が大きく左右されることになります。
ここに記載漏れや不備があると、認定されていないとおかしいはずの等級に、認定されないなんて事態も十分あり得ます。
となれば、適正な賠償金を得ることはできなくなり、当然ながら生活に大きな支障が出る危険もあります。
こういった事態にならないためにも、後遺障害診断書の中身については専門知識豊富な弁護士にチェックしてもらうことを忘れてはなりません。
弁護士であれば、後遺障害診断書の中身をチェックし、記載漏れや不備があれば、担当医師に必要箇所を書き直してもらうよう指示してくれます。
一般の方が判断するのは容易ではないため、後遺障害等級認定が必要になる方、特に目に見えにくい障害(むち打ちや高次脳機能障害など)が出ている方は、弁護士に依頼しましょう。
当事務所での後遺障害等級認定の対応
当事務所では、事前認定と被害者請求であれば、被害者請求を利用するケースが多くなっています。
この理由は、手間がかかることがネックではあるものの、過程をしっかりチェックできますし、何より適切な等級認定が得られる可能性が高いためです。
また、狙った等級認定を得られるように後遺障害診断書等の提出書類をチェックしていくため、希望通りの結果を現実に何件も得られています。
ただし、被害者請求となれば、どうしても被害者側の負担もかかってくるため、そこはやはり話し合いで決めています。
また、狙っていた等級認定を得られなかった場合、異議申し立ても行っています。
この際は、資料集めや新しい証拠を提出することで、適切な等級認定が判断されるよう最大限の努力を行っています。